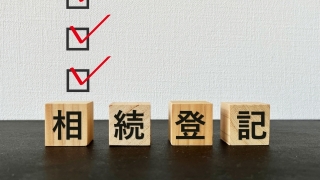 もっと知りたい
もっと知りたい 遺産分割協議の前に知っておくべきこと
令和6年4月1日からの相続登記の申請義務化に伴い、「何年も前に死亡している故人の相続手続きをしていなかった物件があるがどうしたらよいか。」というご相談が増えています。今日は、遺産分割協議自体をされていない方々のご参考になる民法上の問題を取り...
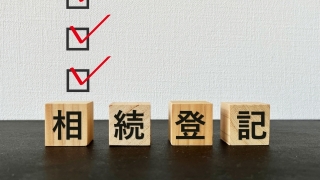 もっと知りたい
もっと知りたい 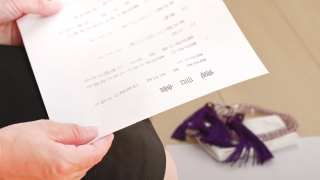 もっと知りたい
もっと知りたい  もっと知りたい
もっと知りたい 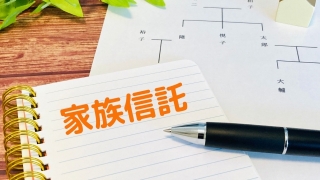 もっと知りたい
もっと知りたい  もっと知りたい
もっと知りたい  もっと知りたい
もっと知りたい  もっと知りたい
もっと知りたい  もっと知りたい
もっと知りたい  遺言相続関連
遺言相続関連  もっと知りたい
もっと知りたい